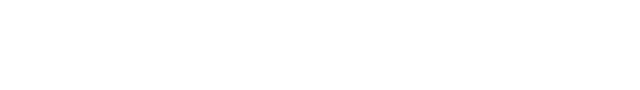オーソモレキュラーを勉強しよう その4 なぜ足が攣るのか
おはようございます!
基本的に日曜日にはゴルフか釣りですが、最近ボーリングにハマっております。
家族で始めたら、自分が一番ハマってきてしまいました^^今週は人生最高のスコアが出て成長を感じております。私は後半戦が強い傾向にあります。
ただ、1日に5ゲーム、6ゲームも投げると手がパンパンになりますね。前腕が攣ったりもします。
では
なぜ攣るのか?今回はその仕組みを考えていきましょう
まずこの私のような過度な運動の場合には 筋疲労・乳酸の蓄積が1番の原因
という事が考えられます。
しかし、一般的に外来に来られる方は筋疲労で来られることは稀です
では他にはどのような病態が考えられるのでしょうか?
筋肉が攣る主なメカニズム一覧
| 分類 | メカニズム | 説明 |
|---|---|---|
| ✅ 電解質異常 | Mg、K、Ca、Naのバランスが崩れる | 特にMg不足が最多原因。KやNaの不足も影響 |
| ✅ 脱水 | 細胞内外のミネラルバランスが乱れる | 水分+ミネラル不足が攣りの引き金に |
| ✅ 神経の異常興奮 | ビタミンB1/B6不足、過緊張 | 神経の興奮性が高まり、誤って筋が収縮し続ける |
| ✅ 血流障害(うっ血) | 長時間の同姿勢、冷え、筋ポンプ低下 | 筋肉が酸欠→けいれん反応が出やすくなる |
| ✅ 筋疲労・乳酸蓄積 | 運動後や持久運動でATP不足 | 筋が弛緩できず収縮したままになる |
| ✅ 副腎疲労 | コルチゾール不足 → 電解質調整が崩壊 | 朝方・深夜につりやすい人に多い |
| ✅ 血糖の乱高下 | 低血糖状態で神経や筋肉が過敏に | 糖代謝が不安定な人(糖質過多)に見られる |
| ✅ 妊娠や成長期の需要増 | Ca・Mg・Kの需要が一時的に増加 | 妊婦・思春期・高齢者に多い |
この中でも、電解質異常がやはり一番の原因かと思います
筋肉は
「Caで収縮」
「Mgで弛緩(ゆるむ)」
という仕組みで動いています。
つまり、こんなバランスです
| 状態 | Caの作用 | Mgの作用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 正常 | 収縮 → 弛緩 → 休息 | 弛緩サポート | 自然な筋運動 |
| Ca過剰 or Mg不足 | 収縮が優位になる | 弛緩できない | 攣る・けいれんが起きる |
つる原因と関連する栄養素
| 栄養素 | 不足時の影響 |
|---|---|
| マグネシウム | 弛緩ができず、筋肉が過剰に収縮して攣る |
| カルシウム | 低すぎると神経伝達異常、筋の興奮性↑ |
| カリウム(K) | 筋肉の電解質バランスを崩し、痙攣リスク↑ |
| ビタミンB1(チアミン) | 神経伝達が不安定に。運動後につりやすい原因にも |
| ナトリウム(Na) | 発汗過多で不足すると、けいれんや脱力が出ることも |
つりやすい人の傾向はその状況で分けるといいでしょう
-
寝ているとき・朝方によく足が攣る → Mg・K不足のサイン
-
運動後につる → 発汗による電解質消耗、B群不足
-
妊娠中・高齢者・糖尿病患者 → Mg不足・インスリン抵抗性との関係あり
その他のオーソモレキュラー的な「隠れ原因」
隠れ要因 詳細 慢性マグネシウム欠乏 サプリで初めて改善されるケース多数。Mgは300以上の酵素反応に関与。 胃酸不足(低HCl) MgやCaの吸収力が低下 → 攣りやすくなる 薬剤の影響 利尿薬、PPI、ステロイド、ピルなどはMg/Kを枯渇させる 甲状腺・副甲状腺の異常 カルシウムの制御異常でつりやすくなることも ビタミンD欠乏 Caの吸収不足→血中Caの維持困難→神経過敏
対策・おすすめ栄養素と食事
| 栄養素 | 摂取の目安 | 食品・サプリ例 |
|---|---|---|
| マグネシウム | 300〜600mg/日 | アーモンド、玄米、にがり、Mgグリシネートなど |
| カリウム | 2,000〜3,000mg/日 | バナナ、アボカド、ほうれん草、芋類(腎疾患は注意) |
| Ca(適量で) | 600〜800mg/日 | 小魚、ごま、豆腐、乳製品(Mgとセットで!) |
| ビタミンB1 | 1.2〜2.0mg/日 | 豚肉、玄米、納豆、Bコンプレックスサプリ |
サプリとにんにく注射、マイヤーズカクテル
-
マグネシウム単体 or カルシウム・マグネシウム複合タイプ
-
ビタミンB群(特にB1多め)
-
スポーツ用の電解質パウダー(Mg・K・Na配合)
当院のマイヤーズカクテルやニンニク注射もおすすめです!
まとめ
| 「足が攣る」原因の多くは… |
|---|
| ✅ Mg不足(最も多い) |
| ✅ Caの分布異常(多すぎてもダメ) |
| ✅ 電解質(K, Na)やB群の不足 |
| ✅ 水分・ミネラルの喪失(汗・利尿薬など) |
さて、そろそろオーソモレキュラーも大詰めです!次回はむくみについてです